こんにちは、はるです。
今回は早生まれかつ発達遅滞の息子が
1歳児クラス4月入園から小規模認可保育園に1年通園して感じたことをまとめています。

この記事を読めば下記の事がわかります。
- 小規模保育園と大規模保育園の違い
- 小規模保育園のメリット
- 小規模保育園のデメリット
- 小規模保育園がおすすめな家庭・子供
育休明け、
保活の時期が迫ってくると

小規模保育園ってどうなのかな?
先生の目が行き届くって本当?

小規模園だと3歳で転園が必要だから大変そう。
こういった大規模保育園vs小規模保育園で悩むも多いと思います。
結論から言うと我が家は
小規模保育園にして大正解でした!!
1年通わせてみると我が家にはいいことだらけで
小規模園に通わせて良かったな〜とつくづく思います。

保育園選びに悩む家庭に小規模園の魅力を伝えたい!
少しでも参考になれば嬉しいです!
体験談を交えながら小規模保育園のメリット・デメリットを
解説していくのでぜひ最後までご覧ください!
小規模保育園と大規模保育園の違い
まずは小規模保育園と大規模保育園にどういった違いがあるのかを簡単に説明します。
| 小規模保育園 | 大規模保育園 | |
| 定員 | 6〜19人 | 数十〜100人以上 |
| 対象年齢 | 0〜2歳 | 0〜5歳 |
| 保育士の配置 | 子供一人一人に目が届きやすい | クラス単位での活動が中心 |
| 施設の広さ | アットホームな環境、園庭なし | 園庭や施設が充実してることが多い |
| 行事の規模 | 行事は少なく小規模 | 大きな行事が多い |
| 転園の必要性 | 3歳以降は転園が必要 | 転園せずに継続してそのまま通える |
こう見ると結構違うように見えますね。
それぞれ特徴があり
家庭状況や子供の性格によってどちらの園が良いか決めていくのがいいでしょう。
小規模保育園のメリット
子供一人一人に目が届きやすい
1クラス7人程度と人数が少ないので、
保育士との関わりが密になり必然的に目が届きやすいです。
保育も1人1人の特性・性格・発達に合わせて行ってくれていると感じました。
また、大規模園とは違い
クラスの担任だけでなく担任以外の全ての保育士さんとも
子供が関わる時間が多く園全体がアットホームな雰囲気なのも魅力です。
一番関わるのはもちろん担任の先生ですが、
園全体がで子供に関わってくれていると親の立場としても嬉しいし安心ですよね!
例えば
我が家は早生まれかつ発達遅滞で、入園前から「活動についていけるだろうか」と不安でしたが
送り迎えの時に先生と親がお互い報連相しながら息子のペースに合わせて徐々に活動に慣れさせてくれましたよ♪

あとは怪我などのトラブルが少ない事でしょうか。
我が子は園児同士のトラブルや怪我をまだ経験していません。
最年長でも2歳児までなので大きい子がいないからかと思います。
行事が少ない
大規模園に比べて行事が少ない事です。
発表会など大きな行事が多いことで園児も職員も練習や準備をする必要があり
プレッシャーになることがあるからです。
特に先生にとっては
行事の準備や練習に追われる事がない分日常保育に集中できるだろうなと感じました。
(発表会前、朝送りに行った時に先生がせっせと衣装を作りながら保育しているのを見た(><))
「行事は多い方がいろんな経験ができて良い!」と感じる方にはデメリットですが
小さい0〜2歳のうちは、
ある程度決まったルーティンで保育する方が子供も安心すると思いますし
練習に追われるよりは行事が少なくてよかったなと思います。
ちなみに我が子が通っていた小規模園では
七夕祭り/秋の遠足/運動会/発表会/お別れ遠足
行事といえば上記の4つのみでしたがちょうどよかったです!

2歳児で“最年長“を経験できる
小規模保育園は2歳児クラスが最年長です。
かつ小規模保育園は異年齢の子供たちと関わる機会が多いです。
2歳児が一番お兄ちゃん・お姉ちゃんになり、
小さい子に対する思いやる気持ちが芽生えやすい環境だと感じました!
息子はもうすぐ2歳児クラスになるので楽しみです(^O^)
感染症のリスクが比較的低い
大規模園に比べて人数が少ないせいか
流行りの感染症などはあまりかかりませんでした。
RSや手足口病、ノロウイルスが巷で流行っていた頃も
「感染者がでています」との報告はありましたが大流行とまではいかなかったです。
これは園児の人数が少ないおかげで先生が子供の体調に気付きやすく
すぐ親に連絡したりと対処ができるからかなあと推測します。
一人一人の生活リズムに合わせてくれる事が多い
「月齢が低くまだ朝寝が必要」
「スプーン食べもコップ飲みもできない」
「昼寝させすぎると夜寝なくなるから昼寝を短くしてほしい」
こういったことも気軽に相談でき、嫌な顔ひとつせず対応してくれたことも
手厚い保育だなと感じました。

毎日の持ち物が少ない
毎日の持ち物が少ないです。
これは結構大きいメリットだと思います。
大規模園では自分のコップやエプロン、毎週の布団の持ち帰りがあると思いますが
息子が通っていた小規模園での持ち物は
- 着替え(各2セット)
- おむつ5枚ほど
- 自分のおやつ皿
- 連絡帳
- 手拭きタオルとループ付きタオル1枚ずつ
以上です。
お布団は園のもの使えるのでお昼寝用バスタオルを週1回持ち帰るだけでした。
どんな雨の日も週末も、
通園バッグ1つもてば帰れたので荷物少ないのありがたいな〜とつくづく感じていました!
小規模保育のデメリット
園庭がない
これは皆さんが思いつく最初のデメリットなんじゃないでしょうか。
小規模園は園庭がありません。
外で遊びにいくには歩くorお散歩カートなどで近所の公園に行くことになります。

歩くようになるとお散歩リングでみんなで歩くので歩くちからがつくのはいいことですが、行き帰りの時間もかかりますし
1年通わせてみて外で思い切り遊ばせられたかと言うとそうではないですね。
3歳で転園が必要である
小規模保育園は0〜2歳までの受け入れのため3歳児からは再度保活が必要になります。
また情報収集したり役所に足を運ばなくてはいけなかったり、
平日保育園に見学に行ったりと
お仕事の休みの都合がつけにくい方や忙しい方に特にデメリットになります。
ただし小規模保育園には「連携施設」が設定されている場合が多く、連携施設に優先的に入園できるような措置が確保されている事があります。
(我が家の園はそうでした)
ですが、連携施設の方針が子供の性格や家庭の事情に合っているとは限りません。
「連携施設に優先的に入園できるなら大丈夫♪」と思わずに
あらかじめ連携施設がどこかは確認しておいた方が良いでしょう。
我が家は3歳で再度保活することがメリットになった!
「え?デメリットじゃないの?」と思うかもしれませんが
我が家では3歳で再度転園のために保活できてよかったと思っています。
なぜなら、0・1歳児ではまだ見えなかった
子の得意なこと・苦手なこと・性格が見えてきたタイミングでその子に合った園を選べるからです。
息子が早生まれなこともあり、我が家が保活していたのは息子が生後半年の時。
その時はまだ子供が何に興味があり何が得意で何が苦手なのか、
どんな性格なのかわかりませんよね。
3歳児でもう一度保活するタイミングには子供の性格もわかってくるので
園の方針・設備・雰囲気をみて選ぶことができるのは結果的によかったなあと思います!
我が家は現在通っている小規模園の連携施設が
“保育方針が我が家に合っている“のと“息子が大好きな絵本が充実してる点“で
この連携施設を転園先の第一候補にしようと考えています。
小規模保育園がおすすめな家庭・子供
- 手厚い保育を希望する方
- 保育士とのコミュニケーションを大事にしたい方
- 早生まれや発達の遅れなど集団生活に不安がある方
- アットホームな雰囲気を希望する方
- 新しい環境に慣れるのにい時間がかかる子
- 行事はあまり多くない方が良いと感じる家庭

子供一人一人に寄り添った温かい保育を受けられるのが大きな魅力。
特に初めての集団生活に不安がある子や、手厚いサポートをもっとめる家庭にはぴったりです!

まとめ
我が家は小規模保育園に入園させて大正解でした。
小規模保育園のデメリットも踏まえた上で、魅力が伝われば嬉しいです。
気になった方は一度施設を見学してみてくださいね。
参考になれば嬉しいです。
他にも保育園に関する記事があるのでこちらも気になる方はぜひご覧ください。
最後までご覧いただきありがとうございます。


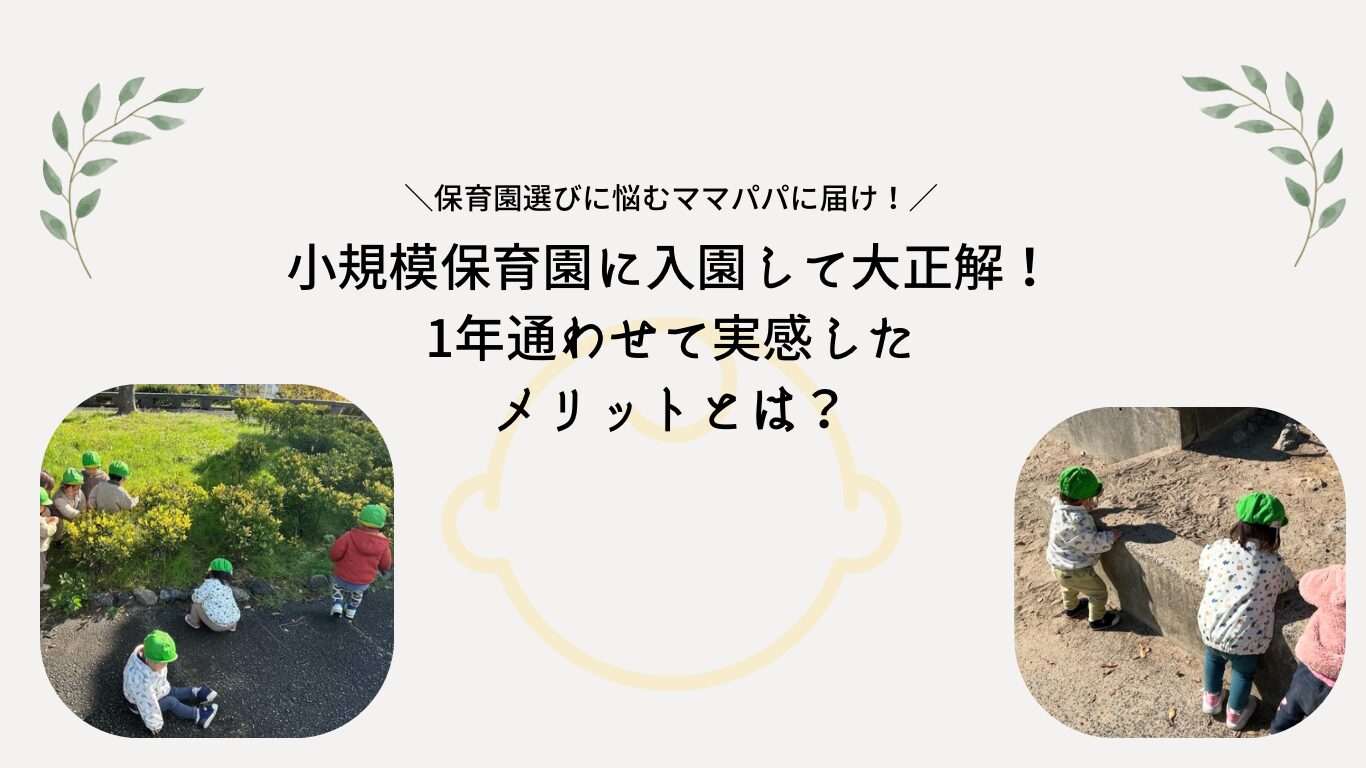



コメント